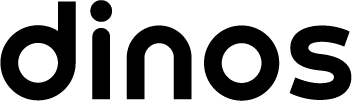車に憧れた
子ども時代
車が大好きな子どもだったという三宅さん。ミニカーの収集に励み、プラモデル作りを楽しんでいたそう。3歳ごろに描いた車の絵は、今でも親が大切に取っておいてくれているとか。
「純粋に、好き、という気持ちから始まり、漠然と車に携わる仕事がしたいと思っていました。そしたら、当時、話題を呼んでいたインスタントコーヒーのCMシリーズにレーシングカーデザイナーの由良拓也さんが出演されているのを見て。車とデザインというキーワードが自分の中で結びつき、なんだか格好いい、と感じたんです」
そんな志を持って、多摩美術大学でプロダクトデザインを学び、大手自動車メーカーの関係会社でデザイナーとして働き始めます。
しかし、しばらく経つと車のデザインには多くの制約があることに気付き、それが今につながる新しいキャリアを開くきっかけになったそう。
「4つタイヤがあってエンジンが搭載されていてボディがあって、という大前提は、どうにもこうにも変えられないんですよね。自分の周囲では家電や家具をデザインしている人たちがいて、その人たちは素材も形も、すべてゼロから考えることができる。羨ましいな、と感じてしまったんです。今となっては、隣の芝が青く見えていたな、と思うのですが(笑)」